樹木と人の協働が未来のいのちを育む大地を育てる
昨日(12/24)は人間の社会では年の瀬を迎えて何かと忙しそうですが、海岸渕の苗木たちも元気に年越しができそうなのかと思い、応援隊・松林副代表と筆者で雫浄化センター育苗場に行ってきました。ポット内の土の乾燥度合いを見て、安心しました。2日前に岩橋事務局員がかけてくれた水が苗木の越冬に役立っている様でした。
 命を育む森の一員として頑張ってもらうためには苗木の都合に人が合わせないといけないことを改めて心に刻みました。
命を育む森の一員として頑張ってもらうためには苗木の都合に人が合わせないといけないことを改めて心に刻みました。
 午後は、原ノ町駅前のホテルで開かれていた「さくらい勝延市政報告会」に出席してきました。彼は、南相馬市鎮魂復興市民植樹祭実行委員会の実行委員長として命を守る森の防潮堤づくりのトップリーダーであり、南相馬市を「脱原発都市宣言」にした市長でもあるので、仲間たちと彼を激励してきました。
午後は、原ノ町駅前のホテルで開かれていた「さくらい勝延市政報告会」に出席してきました。彼は、南相馬市鎮魂復興市民植樹祭実行委員会の実行委員長として命を守る森の防潮堤づくりのトップリーダーであり、南相馬市を「脱原発都市宣言」にした市長でもあるので、仲間たちと彼を激励してきました。
 会場は立錐の余地のないほどの盛況でしたので、集っていた市民から私たちが檄を頂きました。来年6月は、全国植樹祭が森の防潮堤の近くで開催されます。応援隊をはじめ市役所、連合原町地区、市民と共に育てている森の防潮堤を全国の皆さんに観てもらえるように願っています。
会場は立錐の余地のないほどの盛況でしたので、集っていた市民から私たちが檄を頂きました。来年6月は、全国植樹祭が森の防潮堤の近くで開催されます。応援隊をはじめ市役所、連合原町地区、市民と共に育てている森の防潮堤を全国の皆さんに観てもらえるように願っています。
防潮堤に植えた樹木達、苗床で出番を待っている幼木達も元気に新しい年を迎えられるようです。全国の皆さん、南相馬市鎮魂復興市民植樹祭に支援してくださってありがとうえございました。また、お会いできることを楽しみにしています。(南相馬市応援隊 東城敏男)




















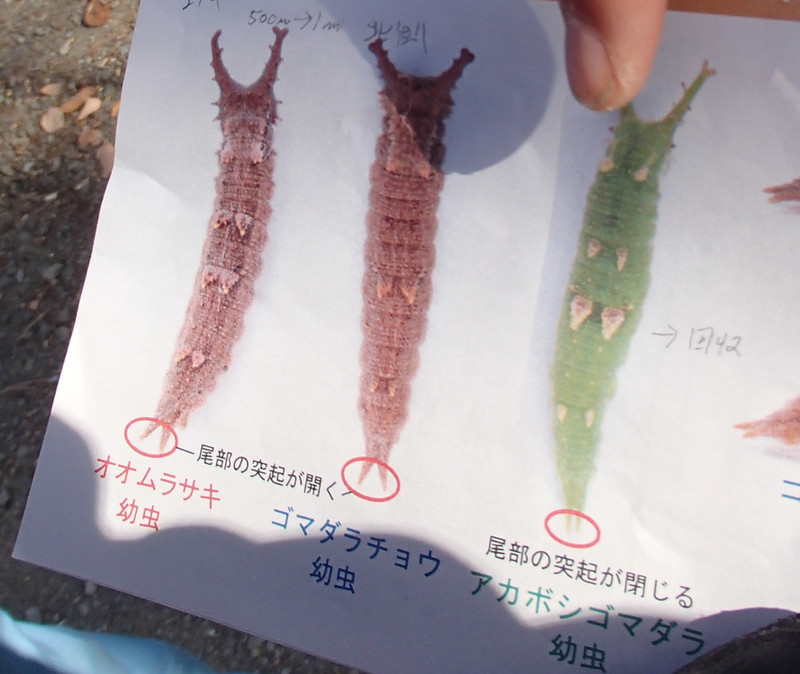



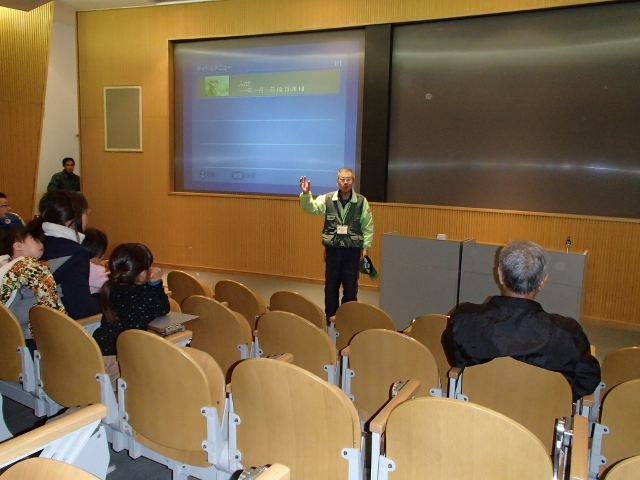
































































最近のコメント