雨上がりの森の中での作業は気分が最高!
足尾の天気は天気予報通りで10時には小雨が止みました。気温は7度で雨上がりの湿気は気持ちがよかったです。
 朝方は雨が降っていたので森作業を変更、エノキとクヌギの移植を行いました。
朝方は雨が降っていたので森作業を変更、エノキとクヌギの移植を行いました。
 午前中に移植を終えようと、手際よく根の周りを伐り取り、一輪車に載せて「オオムラサキ園」(仮称)へ移動。
午前中に移植を終えようと、手際よく根の周りを伐り取り、一輪車に載せて「オオムラサキ園」(仮称)へ移動。
 培養土をたっぷり入れて、根が風で動かないように支柱で幹を支えました。移植は予定通りに終わりました。
培養土をたっぷり入れて、根が風で動かないように支柱で幹を支えました。移植は予定通りに終わりました。
 この園にはミシガン大学生たちの想いが詰まった桜を植えました。ところが若木の樹皮は猿に食べられてしまった箇所があるため、朝の布を包帯代わりにして幹をガードしてやりました。
この園にはミシガン大学生たちの想いが詰まった桜を植えました。ところが若木の樹皮は猿に食べられてしまった箇所があるため、朝の布を包帯代わりにして幹をガードしてやりました。
 昼食休みは、通常総会ではどんな議論をつくっていこうか等を話し合いました。午後は、昨日の「松木の杜」の枯れ草刈りと枝の片づけをしました。杜の半分の枯草を15時まで刈りました。
昼食休みは、通常総会ではどんな議論をつくっていこうか等を話し合いました。午後は、昨日の「松木の杜」の枯れ草刈りと枝の片づけをしました。杜の半分の枯草を15時まで刈りました。
 後は、刈り払い機の点検をして作業終了です。雨上がりのしっとりした春陽はとても身体に良い感じがしました。今日の作業は、鎌田、加賀、小川そして筆者でした。(報告 高橋佳夫)
後は、刈り払い機の点検をして作業終了です。雨上がりのしっとりした春陽はとても身体に良い感じがしました。今日の作業は、鎌田、加賀、小川そして筆者でした。(報告 高橋佳夫)






















































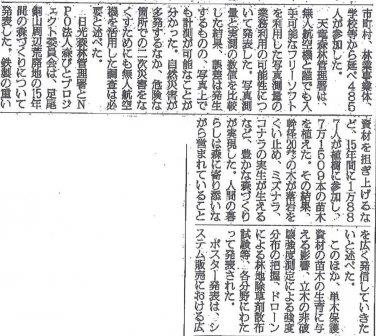













最近のコメント