0157菌を破壊する青森ヒバの役割
5月30日(土)に開催する第9回「足尾・ふるさとの森づくり」では、体験コーナーを用意します。この目的は、人間は森に生かされていることを参加した方々に実感してもらうためです。
その一つが、青森ヒバの効能体験です。以前紹介しました宮大工・加藤吉男さんは300年~400年間生きてきた青森ヒバを使って神社やお寺の新築、修理・復元をしています。ヒバを伐って、自然乾燥させてから人間のために役立てようと、宮大工の技能によって命を吹き込まれさらに何百年以上も生きつづけます。
体験コーナーでは、加藤さんから提供されたこの青森ヒバを鉋で削ってもらい、削ったヒバを持ち帰っていただきます。青森ヒバは、抗菌力、防虫、防臭効果を発揮します。弘前大学教授・佐々木甚一さんチームの実験によると、青森ヒバに含まれているヒノキチオールは0157菌等の増殖を完全に抑え、抑制する、と述べています(先生のホームページより)。また、α‐ビネンという成分は私たちのストレスを和らげる、と言われています。
体験コーナーでは森に入ると清々しい、気持ちが良い、ということだけで満足するのでなく、“なぁーんでか?”ということを解ったうえで森の素晴らしさを、実感して頂きたいと願っています。
石川啄木も渋民村の生活から森に生かされていることを体験し、それを科学的に修得したのでしょうか。啄木がサルに扮して人間を諭している絵本・『サルと人と森』が本日の『上毛新聞』に紹介されました。上毛新聞社のみなさんありがとうございました。 下の写真はカタクリです。この可憐な花や根にも私たちはお世話になっています。
下の写真はカタクリです。この可憐な花や根にも私たちはお世話になっています。
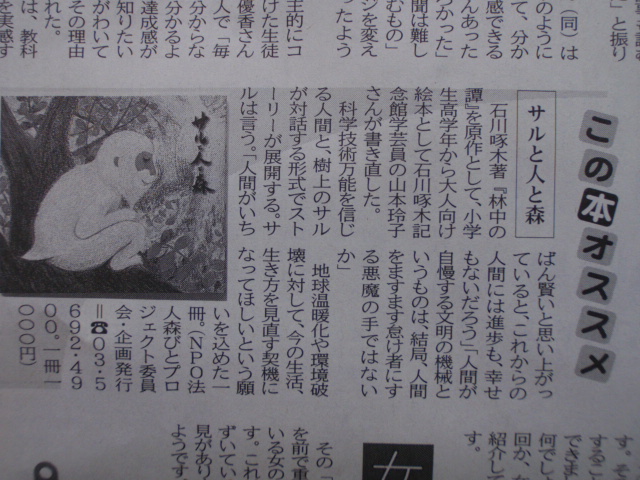



















最近のコメント