心優しい“気合い”に胸が熱くなる森作業
 無風の快晴の朝、気温は1度でした。筆者は今年初の足尾入り、低気圧が南下してくれたので足尾は春日和の陽気のなかで森作業が行われた。
無風の快晴の朝、気温は1度でした。筆者は今年初の足尾入り、低気圧が南下してくれたので足尾は春日和の陽気のなかで森作業が行われた。
 朝、スタッフが足尾入りする前に作業小屋の掃除と薪ストーブを暖め、湯を沸かして11名の皆さを迎えた。ホットコーヒーを飲みながら、癌と戦っている岸井理事長と竹内アドバイザーの様子を報告し、その後、臼沢の森の枯れ草刈りチームと民集の杜育樹チームに分かれて作業を始めた。
朝、スタッフが足尾入りする前に作業小屋の掃除と薪ストーブを暖め、湯を沸かして11名の皆さを迎えた。ホットコーヒーを飲みながら、癌と戦っている岸井理事長と竹内アドバイザーの様子を報告し、その後、臼沢の森の枯れ草刈りチームと民集の杜育樹チームに分かれて作業を始めた。
 久しぶりの臼沢の森階段の登りであったが、シニア達は600段もの階段をへこたれずに登っていた。皆さんの様子は気合が入っている感じであった。1㍍程のススキや枯草を刈り、また、アキグミの枝を伐って植樹祭地の準備をすすめた。作業は予定通りに進み、13時から昼食を摂った。
久しぶりの臼沢の森階段の登りであったが、シニア達は600段もの階段をへこたれずに登っていた。皆さんの様子は気合が入っている感じであった。1㍍程のススキや枯草を刈り、また、アキグミの枝を伐って植樹祭地の準備をすすめた。作業は予定通りに進み、13時から昼食を摂った。
 民集の杜チームは30分程遅れての昼食。食後のお茶を飲みながら、只見町布沢集落支援や「心の森探訪in八幡平」の計画の話し、午後の作業の打合せをした。午後の作業は、竹内アドバイザーが予定していたシロダモの苗作りができなくなってしまったので、奥様から託されたその種を私たちはドロ箱に蒔いた。
民集の杜チームは30分程遅れての昼食。食後のお茶を飲みながら、只見町布沢集落支援や「心の森探訪in八幡平」の計画の話し、午後の作業の打合せをした。午後の作業は、竹内アドバイザーが予定していたシロダモの苗作りができなくなってしまったので、奥様から託されたその種を私たちはドロ箱に蒔いた。
 今日の作業を終えてみると、スタッフの気合は病と戦っている岸井さんや竹内さんへの激励メッセージとなって表れているような気がした。スタッフの皆さん、お疲れ様でした。
今日の作業を終えてみると、スタッフの気合は病と戦っている岸井さんや竹内さんへの激励メッセージとなって表れているような気がした。スタッフの皆さん、お疲れ様でした。
 今夜は、鎌田スタッフからいただいた山芋、松村宗スタッフの家庭菜園の里芋をご馳走になって、森びと強者たちの心優しい気合に乾杯したい。本日のボランティアは、鎌田、松村宗雄、松村健、岡安、小井土、橋倉、加賀、仁平、小川、岡部、太宰、筆者でした。(理事 高橋佳夫)
今夜は、鎌田スタッフからいただいた山芋、松村宗スタッフの家庭菜園の里芋をご馳走になって、森びと強者たちの心優しい気合に乾杯したい。本日のボランティアは、鎌田、松村宗雄、松村健、岡安、小井土、橋倉、加賀、仁平、小川、岡部、太宰、筆者でした。(理事 高橋佳夫)






























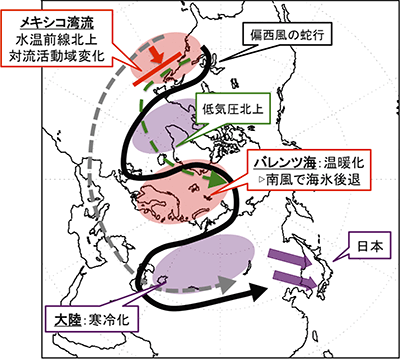



















最近のコメント