森づくり運動の第2ステージを語り合いたい2020年
「松木村 漆黒の闇に 冬の星」(松村宗雄)、「山眠る 鹿の足跡 松木沢」(仁平範義)。この俳句は両氏が年末に送ってくれました。この句にはどんな思いや願いが込められているのでしょうか。
 上の写真は銅の製錬過程で出た滓の堆積場跡です。私たちの森づくりは1902年頃に廃村になった松木村跡地で行っています。この地は、煙害で農作物が育たなくなり、現金収入源であった養蚕の桑の木が枯れる等で暮らしの糧が奪われてしまった所です。この堆積場の西側の草地に2014年から5年間、苗木を植えて森を育てているのが「民集の杜」です。5年前に植えた苗木は樹高5㍍程に生長し、生き物たちのゆりかごになっているようです。
上の写真は銅の製錬過程で出た滓の堆積場跡です。私たちの森づくりは1902年頃に廃村になった松木村跡地で行っています。この地は、煙害で農作物が育たなくなり、現金収入源であった養蚕の桑の木が枯れる等で暮らしの糧が奪われてしまった所です。この堆積場の西側の草地に2014年から5年間、苗木を植えて森を育てているのが「民集の杜」です。5年前に植えた苗木は樹高5㍍程に生長し、生き物たちのゆりかごになっているようです。
足尾の森づくりスタッフの半数は今年で古希を迎えます。その一人が仁平スタッフです。75歳になる松村宗雄さんは、「75という私にとってはひとつの区切りの数字。今年は、この数字を健康で迎える準備をする。健康なくして目的は達成できなということを体験した15年間でした。また、五感を感じるだけでなく、見る五感に今年からチャレンジしたい」、と松村さんの第2ステージを伝えてくれました。
 古希を迎えたスタッフの気持ちは“森づくり活動の第2ステージ”生き方ではないかと思います。筆者もその一人として、「パリ協定」始動年の森づくり運動にチャレンジしていきたいと思っています。
古希を迎えたスタッフの気持ちは“森づくり活動の第2ステージ”生き方ではないかと思います。筆者もその一人として、「パリ協定」始動年の森づくり運動にチャレンジしていきたいと思っています。
筆者のスローガンは、“脱原発・森に寄り添う暮らし(社会)を実現するために心をひとつにする運動”としたい。今年から10年間は、「温暖化を暴走させるのか否かの分岐点」と言われています。その1年目に生きるシニアとして、まずは第2ステージに起ってくれる森びと達と新年の盃を交わして、心をひとつにできればと思っている新年です。(副理事長 髙橋佳夫)













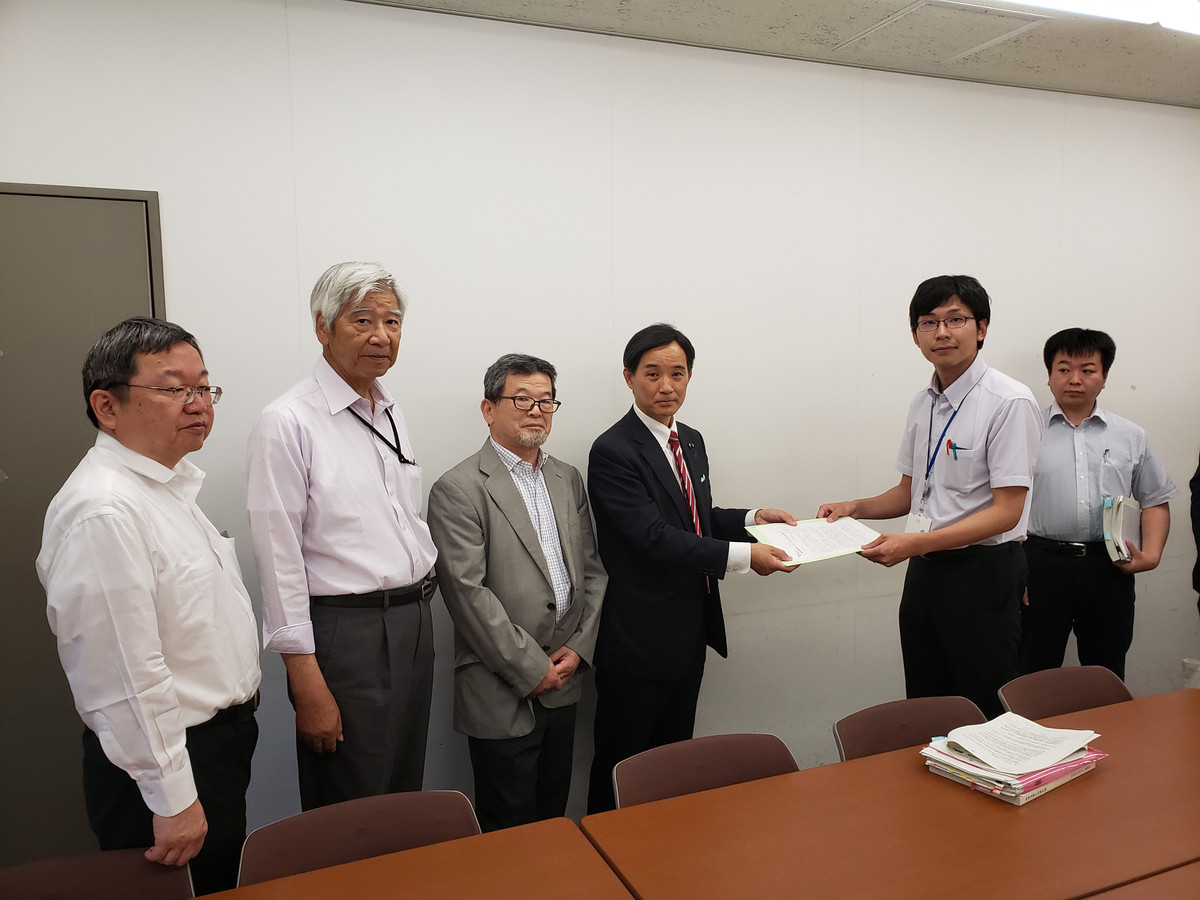








































最近のコメント