人の話を自分の話にしよう
森びらきに参加されました皆さん、木村さんの講演や奥平さんの演奏を聞き、多くの皆さんは何かを感じ取ったのではないかと思います。その後、何かを感じ取った皆さんは、何かを試している方はいますか。
木村さんは30数年間の苦闘のなかで、多くの失敗をしました。その度に彼は、失敗の原因であった自分の固定観念をひとつ一つ捨ててきたと言っています。それを聞いた時、私は木村さんはその上に存在しているから、説得力も自信もあるのだと感じています。何かを試してみないと失敗も成功もありません。それは「フツーの常識」、間違った「固定観念」に騙されたままの自分になってしまいます。
私は本日の朝から実験をしています。自分の主食である米がどんな米なのか、を試しています。木村さんが話しをしてくれたように、一握りの米をコップに入れ、約同量の水をコップに入れてラップする。ラップには2、3個の穴を開けて、暖かいところに約一ヶ月置いておく。一ヶ月後にそのラップを開けて、臭いと色などを見るという実験です。木村さん曰く、その米を食べていると人間の身体はどうなっていくのかを想像してみてください、と。
人間の根は食、その根がどんな食を食べているのか、食は誰が生産しているのか、農薬漬けの食を自分で試して、何かを感じっことを自分のものにすることが木村さんの講演ではないでしょうか。







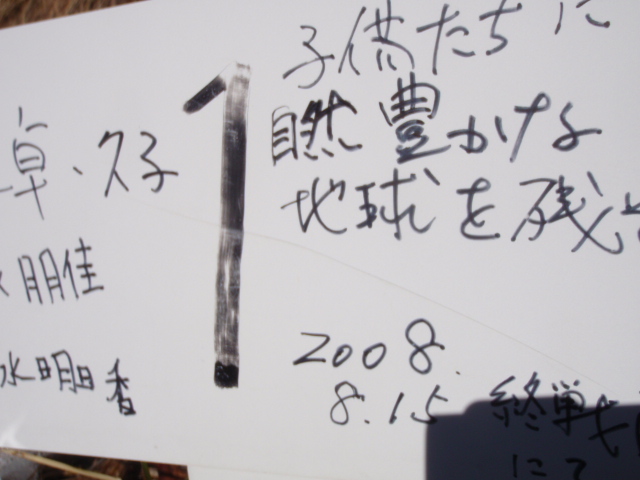







最近のコメント