昨日(2/27)、南相馬市で鎮魂復興市民植樹祭市民サポーター講座の2回目を開催しました。午前と午後合わせて15名の市民の皆さんに参加いただきました。相馬農業高校の学生2名にも参加していただき森の防潮堤づくりの意義など学びました。先週に引き続き、事務局(筆者と宮原)が提起を行い、6名の森びとインストラクターとみちのく事務所・泉山所長と鎌田事務次長にも協力をもらいました。
 参加された方からは、「当日のイメージを持つことが出来た」「マルチングの重要性が分かった」「縄の結び方が難しかった」「縄を自宅に持ち帰り当日までに出来るようにします」など感想が出されました。
参加された方からは、「当日のイメージを持つことが出来た」「マルチングの重要性が分かった」「縄の結び方が難しかった」「縄を自宅に持ち帰り当日までに出来るようにします」など感想が出されました。
 今回の植樹祭は3回目となります、机上の学習でなく、手を使い体を使い実践的に学び、植樹祭を成功させようと誓い合いました。
今回の植樹祭は3回目となります、机上の学習でなく、手を使い体を使い実践的に学び、植樹祭を成功させようと誓い合いました。
前日は昨年の植樹会場と雫浄化センター脇の苗床の視察と前苗床の整理作業を行いました。参加された皆さん、お手伝いいただいた森びとインストラクターの皆さんありがとうございました。植樹祭当日は全力で応援していきましょう!!
 (事務局・水落)
(事務局・水落)
昨日13時からは、大野理事、応援隊の事務局スタッフ・東城さんと筆者は、南相馬市の苗床にある苗木のうち、3月27日開催される第3回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭で使用するための選定を公益財団法人瓦礫を活かす森の長城プロジェクト・技術部会の箱崎祐二さんと一緒に行いました。これらの苗木は各所で3年間育ててきた苗木ですので、1本でも多く植えることができ、いのちを守る森の防潮堤として役立ってもらいたい思いを訴えながら、あわせて育苗方法(土選びや3か月に1度は化成肥料をあげたほうが良いなど)、苗木の置き方(風対策など)についても教えていただきました。

15時30分からは、ひがし生涯学習センターにおいて、南相馬市鎮魂復興市民植樹祭応援隊第2回総会が開催され、26名が参加をしました。主催者あいさつで副代表の渡部さんからは1年間のお礼と今後の活動への協力のお願いが話されました。

来賓あいさつで森びとの大野理事からは、日頃の育樹・育苗活動へのお礼とますますの応援隊の拡大そして4月16日開催の市民フォーラムの成功に向けて一緒に頑張ろうと話がありました。

その後、1年間の活動を振り返り、今後1年間のスケジュールが提案されました。昨年と違う活動として4月16日に森びととともに実行委員会をつくり、市民フォーラムを開催することと6月に育苗・育樹指導セミナーを開催することを決めました。その後、2名の方から「森の防潮堤づくりは素晴らしいこと。完成後の全体像を示してもらいたい」「昨年の植樹祭では植樹リーダーの方の説明が聞こえなかったのと、競争ではなく落ち着いて植樹をしていただきたい」などの意見が出されました。新しい役員体制は、代表には新たに渡部俊一さんが就き、副代表には松林英夫さんと菅野長八さん、事務局に小川尚一さん、山田悦子さん、岩橋孝さん、事務局スタッフには新たに丹しげ子さんが加わりました。なお、前代表の西銑治さんは顧問に就くことになりました。1年間よろしくお願い致します。

16時45分からは、南相馬市・桜井勝延市長と面会しました。それは4月16日に開催する市民フォーラムへの出席の依頼と南相馬市が発出した脱原発都市宣言で目指すべきものを反映させていくために話を伺うためでした。市長からは「原発立地都市ではないけれど、これだけの被害があった。原発はダメということ」「原発に頼らないエネルギー政策は確実に前に進んでいる」「今年のスローガンは、全世代を通じて元気な街づくり」などと言われていました。また、「現在、0~2歳児の待機児童が90人もいる。2年前から幼稚園・保育園の無料化をした結果、1年前から園児が218人増えた。今は保育士の確保が課題」などうれしい悲鳴と市の実態が知られていないことを嘆いていらっしゃいました。
森びととJR東労組が市に送った苗木の管理についても気にしていただき、アドバイスもいただくことができました。帰路では南相馬市の復興の応援を確実に仲間を作りながら進めていこうと確認しあいました。桜井市長、お忙しい中、貴重な時間をありがとうございました。

(事務局・小林敬)



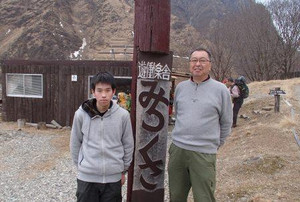
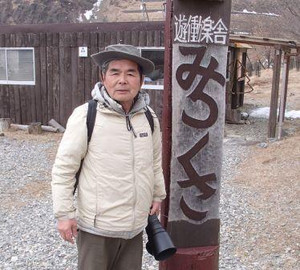






































































最近のコメント