安全に妥協は許されない
昨日は古河機械金属㈱足尾事業所の案内で、廃坑後の施設を見学しました。備前楯山の周囲の山々は江戸時代から掘られ、その坑道は延べ1000㎞を超えると言われています。この坑道には湧き水が流れ、水には様々な鉱物が含有され、化学変化を起こしながら水は流れています。この水は害にならないように中和され、川に流されます。しかし、水に流されてきた様々な含有物は専用のたい積場に溜め、川に流れないように管理しています。
これらの施設は各箇所で毎日点検されています。大雨や地震などが起こったときには、徹夜で監視している、といいます。安全が確保されている影には安全を守る人がいました。見学した施設は50年間以上も人の目と手で監視されていました。
ところで、本日は日光中禅寺湖周辺の「千年の森」(私達が言っている森)を、東京農大の学生さんと一緒に調査する予定でした。本日の天気予報は雨ですので、標高1500㍍付近は雪です。足尾から中禅寺湖へ車で向かうには、雪用タイヤもしくはチェーンが必需品です。ところが足尾事業所で森びと号タイヤをチェックすると、雪用タイヤに交換してあるはずの森びと号はノーマルタイヤでした。急遽、日光市内でチェーンを買い求めようとしましたが、店には売っていませんてした。
雪の「千年の森」調査は断念し、東京へ引き返しました。何事も安全が第一ですが、それを確立させていくためには基本的な点検(チェック)と判断(断念)の大切さを痛感しました。






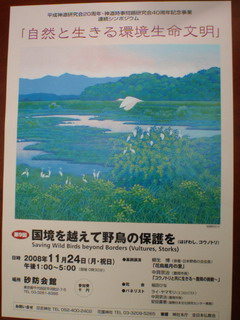











最近のコメント