悔しさをバネに、決意を新たに!
昨日(2月22日)、横須賀石炭火力控訴審判決があり、清水副代表と一緒に参加をしました。東京高等裁判所101号法廷は9割方の席は埋まりました。11時に開廷し、裁判長は「本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は原告が持つ。以上」とだけ言い、怒りの声が響く中、僅か10秒ほどで閉廷しました。やましいことがなければ、堂々としていれば良いものの、逃げるように法廷を立ち去る姿には怒りとともに呆れを感じてしまいました。
その後の報告集会では、小島延夫弁護団長からは原告側の主張を認めつつ、否定をする裁判官の保身について語られ、①CO2の累積的影響を認識しながらも、横須賀石炭火力発電所からの排出を許容している、②気候変動は地球規模の問題と認めながらも原告への影響はないとしている、③合理化ガイドラインの適用が妥当と判断する根拠が環境アセスメントの趣旨に反している等、判決に対する3点の矛盾点が述べられました。
原告団長の鈴木陸郎さんからは、「判決の言い渡しは、ほんの数秒で終わった。衝撃を受けた方もいると思うが、あの場面は、あれ以上あの場に裁判官がいることができない、ということの表れだったのだと思う。内容的には圧勝している闘いをやってきているということ。ここでやめたら自分たちは諦めたのかということになってしまう。最高裁判所に最後まで判断を仰ぎたい。ぜひご賛同いただきたい。また、この裁判を通じて学んだのは、今の社会が、このままの状態で将来に渡していいのかという状況にあるということ。CO2を出していることによって今の社会が成り立っている、そんな社会の仕組みを作ってしまった、そういう責任があると思う。それを解決する方法を目指さないと、次の世代に申し訳ない。その方法として、我々が武器にしていた環境アセスメントはものすごい武器になるはず。環境アセスメントの仕組みは、そんな法律にしていかないといけない」と決意が述べられました。
 これまで、地元・横須賀市民を中心に、気候危機や大気汚染への影響を懸念し、「反対」の声をあげ続けています。石炭火力は地球温暖化の最大の原因であり、G7でも全廃すると約束が交わされており、まずもって減らすべきものです。
これまで、地元・横須賀市民を中心に、気候危機や大気汚染への影響を懸念し、「反対」の声をあげ続けています。石炭火力は地球温暖化の最大の原因であり、G7でも全廃すると約束が交わされており、まずもって減らすべきものです。
 世界では訴訟によって市民が勝利をした例もあることから、決してあきらめずに、化石燃料を使用する事業主体にプレッシャーをかけ続けることが大切であり、闘いの歩を止めるわけにはいきません。最高裁に上告することが確認され、熱気あふれる報告集会そして次の闘いへの決起集会となりました。
世界では訴訟によって市民が勝利をした例もあることから、決してあきらめずに、化石燃料を使用する事業主体にプレッシャーをかけ続けることが大切であり、闘いの歩を止めるわけにはいきません。最高裁に上告することが確認され、熱気あふれる報告集会そして次の闘いへの決起集会となりました。
https://yokosukaclimatecase.jp/news/nishin-hanketsu/?s=03
(運営委員・小林敬)


































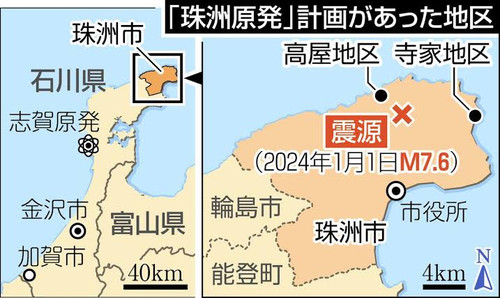





























最近のコメント