先月、アメリカ・ニューヨークで開催された国連気候行動サミットに向けて、“温暖化防止”、“気候正義”を求めて、世界中で子どもたちや若者を中心に150カ国、4,500ヵ所、700万人以上の参加者が手を取り合って声をあげました。
USATODAY紙によると、今回の気候デモへの参加者は、アメリカ・ニューヨーク25万人、オーストラリア・メルボルン10万人、ドイツ・ベルリン27万人、ドイツ全体150万人、イギリス・ロンドン10万人、東京5,000人と報道しています。
 (9月20日朝日新聞)
(9月20日朝日新聞)
このまま地球温暖化が進み異常気象が当たり前のように頻発すると、一番被害を受けるのは未来ある子供たちや若者世代であり、その象徴的存在がスウェーデン人のグレタ・トゥーンベリさんです。
この子供たちや若者の声に応えた企業がありました。イギリスの化粧品会社・RUSH(ラッシュ)は世界38カ国の店舗とオンラインショップで営業を停止し、参加は社員の任意ということでした。また、スノーボード用品メーカーのBURTON(バートン)でもオフィスと店の営業を停止し、それぞれのデモ行進に参加をする場合は、勤務扱いとなり、参加をしない場合は有給扱いとしたそうです。この他にも、フットウェアブランドのKEEN JAPAN、アウトドアメーカーのパタゴニア日本支社、通販会社のフェリシモなどもグローバル気候マーチへの賛同をしました。
 「国連気候サミット」を呼びかけたグテーレス事務総長は閉会スピーチで、「77か国が2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げ、70か国が2020年までに国としての対策を強化させると表明した」と話をしました。しかし、ここには温室効果ガス排出上位5か国(中国、アメリカ、インド、ロシア、日本)は含まれていないようです。環境汚染をしている上位5か国は、世界の子どもたちや若者の声を無視し、グレタさんから「温暖化防止のための行動を怠り続けるならば、あなたたちは悪だ」と、言われてしまいました。
「国連気候サミット」を呼びかけたグテーレス事務総長は閉会スピーチで、「77か国が2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げ、70か国が2020年までに国としての対策を強化させると表明した」と話をしました。しかし、ここには温室効果ガス排出上位5か国(中国、アメリカ、インド、ロシア、日本)は含まれていないようです。環境汚染をしている上位5か国は、世界の子どもたちや若者の声を無視し、グレタさんから「温暖化防止のための行動を怠り続けるならば、あなたたちは悪だ」と、言われてしまいました。
このサミットでは日本政府、安倍首相のいつもの元気はなく、小泉進次郎環境大臣のスピーチも意味不明の”セクシー”という言葉が失笑されました。その上、日本はG7の中で唯一、石炭火力発電を国内外で推進していることに世界各国から非難をされてました。
当会は、地球温暖化に対して何か効果的な対策を打つことはできないか、未来を生きる子供たちと私たちのために地球を守りたいと15年間森づくりをすすめ、足尾では70,000本以上の木を植えてきました。地球温暖化防止には、温室効果ガス、中でも二酸化炭素の大気中の濃度を増加させないことが重要であり、森が吸収源として大きな役割を果たしています。
今年5月、フィリピンでは卒業を控えた小学校から大学までの生徒らに、卒業の条件として“10本の木を植えること”を義務付ける法律「Graduation Legacy For the Environment」(環境を改善するための卒業遺産)が制定されました。法案を起草した国会議員のゲーリー・アレジャノさんは「この法律は若者たちの意識を高め、サスティナブル(持続可能な)な資源活用を促進していく」、「毎年小学校から1,200万人、高校から500万人、大学から50万人が卒業する。毎年少なくとも1億7500万本の新しい木が植えられることになる」などと語っています。森林破壊により、毎年森林が現象している現状を鑑み、次代を担う若者に植林を通じて二酸化炭素の吸収や森林破壊防止のほか、環境への関心を高めるために多少強引かもしれませんが、良い環境教育だなと感じました。
(2010年、川崎市古川小学校での環境教育授業の様子)
日本でも学生に限らず、地球温暖化防止のために国民参加の植林活動を官民が一緒になって進めていくことこそ、グレタさんら若者たちの行動に応えることになるのではないかと思います。(東京事務所・小林敬)
 全員が集合後、コーヒーを飲みながら、責任者の鎌田スタッフより、「今日は東京から精鋭たちが来ました」と、激励を受けるなか、午前中は臼沢の森の草刈りと苗床にあるポット苗の草取りの2手に分かれて作業を行うと、説明を受けました。
全員が集合後、コーヒーを飲みながら、責任者の鎌田スタッフより、「今日は東京から精鋭たちが来ました」と、激励を受けるなか、午前中は臼沢の森の草刈りと苗床にあるポット苗の草取りの2手に分かれて作業を行うと、説明を受けました。 第4期インストラクターの山本勉さんは、8年ぶりに袖を通したつなぎを身に纏って、作業を前に張り切っておられました。
第4期インストラクターの山本勉さんは、8年ぶりに袖を通したつなぎを身に纏って、作業を前に張り切っておられました。
 現場に到着すると、膝や腰まで生えている下草刈りに苦労しました。
現場に到着すると、膝や腰まで生えている下草刈りに苦労しました。 苗床では、ポット苗の草取りを行いました。ミミズが元気よく動いていましたので、良い土を作ってくれるでしょうか。
苗床では、ポット苗の草取りを行いました。ミミズが元気よく動いていましたので、良い土を作ってくれるでしょうか。













































































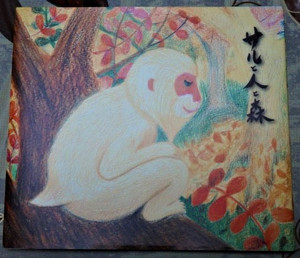










最近のコメント