8月28日(日)、東京都西巣鴨にある大正大学で「まちから村からの連帯でひとりぼっちの高齢者をなくそう」をテーマに第30回日本高齢者大会が開催されました。
日本全国から高齢者が集まり、高齢者が元気に暮らせる・活躍できるような様々なテーマでの学習会やシンポジウム、討論会が行われました。

当委員会からは、足尾で森づくりに励むスタッフ6名が「東京都に常緑樹の森をつくろう!高齢者の孤立予防」をテーマの分科会に参加をしました。

50名ほどが参加した分科会では、当委員会・高橋副理事長が司会を務め、まず初めに宮脇昭先生の提案を受け「森の防潮堤」づくりに取り組む一般社団法人 森の防潮堤協会 日置道隆理事長(輪王寺住職)より基調講演が行われました。

日置理事長からは、2011年3月11日に発生した東日本大震災後、宮脇先生と津波被災地の植生調査を行い、岩沼市で千年希望の丘植樹祭を開催し「いのちを守る森の防潮堤」づくりに取り組んできた意味について話がされました。


「あらゆるものは、その一瞬の間にも変化を繰り返しているが、私たち現代人は、今あるものが永遠に存在すると錯覚し、そこに執着が生まれ苦しんでいる。自然の森は自ずと存在し、森の中では絶えず生命の生滅を繰り返し、全体的に絶妙なバランスを保ちながら存在する」と自然観が語られ、5年間で約25万本の土地本来の木々を植え、植樹を通して「森づくりは人づくり」であることや、「科学と自然とが調和した社会をいかに築くか」「人類は自然と調和し共生する以外の道はない」と東日本大震災で得た教訓が話されました。土地本来の木々を植え、多様性のある森をつくることは新たな文明を築く第一歩です。森の破壊が文明の危機になることを歴史が証明していることから、東京都に住む人たちに対して、「人工物の塊である大都市は災害に弱い。未来の子供たちのために豊かな森をつくろう」と東京オリンピックの森を提唱されました。

続いて、どんぐり育て隊杉並 東京西部保険生協 河合政美専務理事長より、宮脇昭先生の指導によって常緑樹の苗をつくり、その苗を東京都内に植えることが提案されました。その問題意識として、首都直下型地震発生の可能性。東京の水、土地、環境を守ること。地震災害、水害からの被害を軽減すること。また、孤独死、孤立死が毎年3万人に上り、男性の一人暮らしの高齢者が増えていることから、高齢者の地域とのつながりをつくることが述べられました。
この運動を通じて、「高齢化社会」に進む中で、高齢男性が中心となり木を植え、子供たちやお父さん、お母さん、市民全体へ広げていくことで孤立予防につながり、様々な世代の人たちと共に自然に触れ、世代間交流も進むこと。防災林で首都直下型地震時の火災の減災、環境保全、ヒートアイランド防止の役割が目指されています。
課題として述べられたことは、どこに植えるのかということ。そして、行政の理解と支援がなければ出来ないことであり、住民と行政のまちづくり運動をつくりだしていくことです。30年先を目指し、人々の心に木を植え、木造密集地、海岸線や低地をはじめ東京のすべての町で森づくりを行いたい。当面は苗を植える場所を確保し、数年後には植樹を行いたいと熱い思いが話されました。

休憩ののちに討論が行われ、全国から参加された皆さんから活発な意見が出されました。
・岩沼市での森の防潮堤づくりはすばらしい取り組み。マンパワーがどのように結集したのか。 お金もかかるが、行政とのかかわりをどのようにつくったのか。
・南海トラフ地震に備えた対策を検討している。堤防より木を植えたほうが良いと聞いた。かなり広い場所と壮大な工事が必要。防潮堤の大きさはどのくらいになるのか。
・過疎化でクマやシカの被害が発生している。人が入らず土砂災害につながっているどう思うか。
・東京都狛江市に住んでいる。多摩川と野川に挟まれた坂のない平らな町で8万人ほどが住む。縄文から人が住み100以上の古墳があったが住宅開発で12基しか残っていない。武蔵野の面影がなくなっている。学校の統合で廃校となった学校跡地を里山にしようと訴えている。体育館を劇場に、学校をホテルやレストランにできる。東京に森をつくろうとする人がいるのは心強い。
・東京には植木屋は増えない。仕事では庭を壊すほうが多い。庭に植木1本植えない。伐採ばかり。ゆとりのなくなった世の中になってきている。他
出された意見に対して、日置理事長、河合専務理事長、そして、森びと高橋副理事長からコメントが述べられ、盛況のうちに分科会が終了しました。

地球温暖化による異常気象によって豪雨災害が頻発しています。東京の下水が許容できる降雨の量は1時間に55mmと言われ、昨今の豪雨は1時間に100mmが当たり前のようになっています。防災・減災のための都市部への森づくりは急務の課題であることが、基調講演や活動報告、参加者からの意見でも明らかとなっています。
どんぐり育て隊杉並の河合専務理事長は「都心の中で、どう火災に強い街をつくるか。東京はウオーターフロントで人口埋め立て地に高層住宅を建設してきた。そういうところに木を植えて減災につなげていくこと。東京オリンピックも緑の多いオリンピックにしたい」と抱負を語ってくれました。
森びとの高橋副理事長は「12年前、地球温暖化防止のために木を植えようとNPO法人森びとプロジェクト委員会をつくった。死ぬまでに何をつくるか。森をつくることは未来をつくること。10年先、20年、子供たちに何を残すのか。暮らし方の問題、暮らしを見直そう」と高齢者の生き方について投げかけられました。
全国の皆さんと、山と心に木を植えることのできた高齢者大会でした。
(報告者 東京事務所・清水 卓)








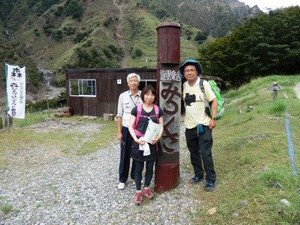

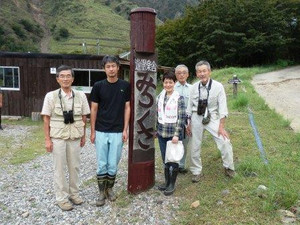

























































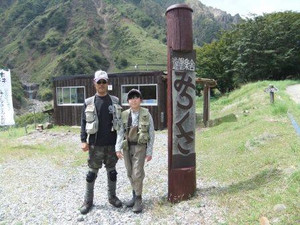
















最近のコメント