5月27日に開催されたシンポジウムでパネラー報告された樹徳高校OB・神田涼さんの後輩の皆さんから、シンポジウムの感想が届きました。
神田さんは高校生時代に環境教育に熱心な先生に誘われ、足尾の荒廃地の森づくりに参加。現在、大学の研究で地球温暖化の原因となる温室効果ガス・CO²の削減に向けた研究に取り組んでいます。技術開発にも取り組んでいますが、これ以上地球を暖めないためには木の有効活用と森林や海が吸収できる量の排出に制限すべきと、私たちの暮らしや経済システムの見直しを提言されています。
後輩の皆さんから届いた感想をお届けします。

《高校生Aさん》
今日の環境シンポジウムを経て、発表された4名の方々の話は全てが実体験だったので、ニュースで知るものや本やネットで見るものとは異なっていて興味深かったです。
特に、発表者それぞれが地球環境危機の影響を具体的に述べていて環境危機の実感が湧きました。
私は始めて「シンポジウム」というものに参加したのでそれぞれの専門分野を持った参加者の話を聞けて良かったです。時には各自の持ち時間を大幅に超えてまで話に夢中になる方もおられて興味深かったです。
《高校生Bさん》
教科書で学んだこと以外のことを知る事ができた。太陽光発電の電力を使って飲食店経営と自家用車の発電をこなせることに驚いた。また参加していた多くの人が、若者が環境問題や社会問題に関心を持つことが必要だと言っていたので勉強だけでなく世界にも目を向けたい。
 (2017年 民集の杜での植樹体験)
(2017年 民集の杜での植樹体験)
 (2017年 民集の杜 ”いのちの木を植えたぞー!”)
(2017年 民集の杜 ”いのちの木を植えたぞー!”)
《高校生Cさん》
貴重な体験になりました。CO²を減らすために経済抑制をするという考えは革新的だと思いました。しかし短期的に見るとデメリットがやはり大きいのではないかと思います。地球のために経済発展を止めろというのは南北問題の原因にもなっているので、抑制が最善とは思えません。私には良案が浮かびませんが、今日の経験を参考に精一杯模索しようと思います。
《高校生Dさん》
地球環境という共通のテーマに対して、いろいろな立場の人からの意見を聞くことができました。神田先輩の発表は、経済の抑制という視点が新しく、日々の生活をダラダラと過ごすのではなく何事にも疑問を持つことが重要なのだと感じました。私も少し研究職に興味があるので、とてもいい機会になりました。今日はありがとうございました。
 (2018年 民集の杜の育樹・下草刈り)
(2018年 民集の杜の育樹・下草刈り)
 (2018年 民集の杜 生長の早い幼木は背丈ほどに)
(2018年 民集の杜 生長の早い幼木は背丈ほどに)
《高校生Eさん》
今日の地球環境に関するシンポジウム、とても面白かったです!普段、環境について深く聞く機会がないので、環境について知る良いきっかけになりました。
神田先輩の、カーボンニュートラルのお話を聞いて、もっと詳しく知りたいと思いました。二酸化炭素を減らすために、木を伐採するという方法や、経済活動を抑制するという方法を聞いて、そんなやり方もあるのかと驚きました。自ら足尾銅山に行って実際に感じたことから研究に繋げていくことが、より説明に説得力が増すこともわかりました。疑問に思ったことも答えていただけて良かったです。森林を伐採する上でかかるコストのことや、どうやって経済を抑制していくのかについてはまだ解決策がないことを知って、自分なりにも考えてみようと思いました。
発表の内容はもちろん素晴らしかったのですが、資料や原稿のまとめ方という点も素晴らしくて、私も神田先輩のように発表が上手くなりたいと思いました。またこのような機会があったら積極的に参加しようと思います。

(2023年5月 多様な生物の暮らす杜に生長)

群馬県桐生市内を流れる渡良瀬川の源流に位置する日光市足尾町・旧松木村。樹徳高校の皆さんが松木村跡の植樹地「民集の杜」に植えた木々は大きく生長しています。40cmほどだった苗木は4mほどに生長し、一生懸命CO²を吸収していることでしょう。
理科部の皆さんも、是非足尾の杜の観察と植樹にいらしてください。お会いできる日を楽しみにしています。
(報告:清水 卓)




































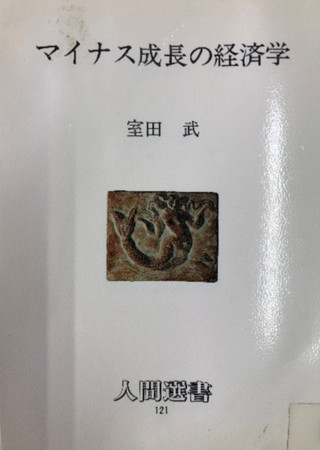

最近のコメント