森の防潮堤に植えたヤマザクラの花を見に来てください
昨日の強風からうって変わって、春めいたあったかい日差しをうけた今日の作業は、新設した倉庫側面の汚れ落としの清掃と苗木のチェック、道具類のメンテナスでした。
 南相馬市の育苗場では、昨日の大雨が苗木たちには恵みの雨の様でした。ヤブツバキの葉の緑は鮮やかに映えており、育てている私たちにとっては心が休まりました。
南相馬市の育苗場では、昨日の大雨が苗木たちには恵みの雨の様でした。ヤブツバキの葉の緑は鮮やかに映えており、育てている私たちにとっては心が休まりました。
 今年の植樹祭は小高区塚原地区で開催予定です。今年の植樹は、8年前の大震災・フクシマ原発事故で大きな被害があったこの地区では初めてのことです。第7回の南相馬市鎮魂復興植樹祭は6月2日(日)に開催されますので、私たちはそこに植える苗木を丁寧に、そして心を込めて育てていくことを誓い合いました。
今年の植樹祭は小高区塚原地区で開催予定です。今年の植樹は、8年前の大震災・フクシマ原発事故で大きな被害があったこの地区では初めてのことです。第7回の南相馬市鎮魂復興植樹祭は6月2日(日)に開催されますので、私たちはそこに植える苗木を丁寧に、そして心を込めて育てていくことを誓い合いました。
 その前の4月13日には第1回植樹会場(2013.10・6)において観察・観桜会を計画しています。間もなく案内をしていきますので、是非、皆さんのお越しをお待ちしています。
その前の4月13日には第1回植樹会場(2013.10・6)において観察・観桜会を計画しています。間もなく案内をしていきますので、是非、皆さんのお越しをお待ちしています。
今日の作業は、岩橋さん、恵美さんそして筆者夫妻でした。(報告 東城敏男)














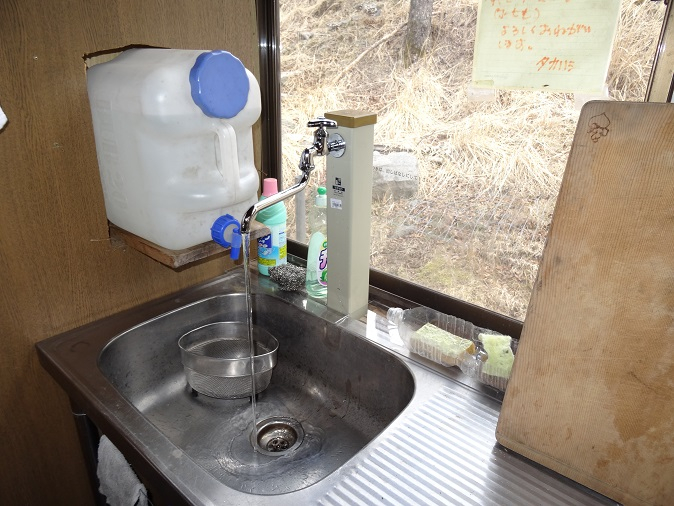






























最近のコメント