久しぶりの森作業に心わくわく、筋肉痛も久しぶり。
2月25日、足尾に向かう途中で見た日光連山は雪化粧でした。久しぶりの足尾森作業日です。前回(2/9)は大雪の影響で中止になり、約1か月ぶりに会う森ともに「お疲れ様。久しぶりです。元気でしたか?」とのあいさつでした。寒い日が続きましたが、今日は9:30、気温は2℃と比較的暖かです。雲一つない快晴です。思わず、携帯カメラで動画を映していました。下のほうでは、ピューと鳴き声がしたので見るとシカが出迎えてくれていました。
 今日の責任者大野さんから作業の説明がされ、午前中は、以前の苗床に植えた桜の木の幹ガードを補強と福原さんから伝授されている獣害柵の補強をする事にしました。午後からは、「りんねの杜改良地」の桜が猿か鹿に樹皮を食べられてしまっているので、幹ガードで保護することになりました。
今日の責任者大野さんから作業の説明がされ、午前中は、以前の苗床に植えた桜の木の幹ガードを補強と福原さんから伝授されている獣害柵の補強をする事にしました。午後からは、「りんねの杜改良地」の桜が猿か鹿に樹皮を食べられてしまっているので、幹ガードで保護することになりました。
打ち合わせ風景
 スカート部分を5枚つなぎ合わせます。突起部分を引っ張り上げて繋ぎますが、結構力技です。
スカート部分を5枚つなぎ合わせます。突起部分を引っ張り上げて繋ぎますが、結構力技です。
 3本鉄筋を打ち込み、5枚繋げたスカートを縦に使い木を囲みます。
3本鉄筋を打ち込み、5枚繋げたスカートを縦に使い木を囲みます。
 針金で鉄筋と金網を結び付けて出来上がり
針金で鉄筋と金網を結び付けて出来上がり
 最後にみんなでジャンダルムをバックに記念写真。
最後にみんなでジャンダルムをバックに記念写真。
 桜の木10本、イチョウの木2本の補強を完成させ、11:30頃に終了しました。皆さん、「今日はあったかいなぁ」と口々に言っていました。
桜の木10本、イチョウの木2本の補強を完成させ、11:30頃に終了しました。皆さん、「今日はあったかいなぁ」と口々に言っていました。
作業小屋に戻ると、先日小柴さんと友人たちがCハウスを取り壊してくれましたが、ビニールが凍り付いて剥がれませんでした。今日は暖かく土が緩んでいるので一部を除いて剝がすことが出来ました。 午後からは、「りんねの杜土地改良地」の桜の樹皮が食べられて幹が裸状態になっているので、幹ガードで守っていきます。桜の木は美味しいのか、ほかの木よりも被害が多くなっています。
午後からは、「りんねの杜土地改良地」の桜の樹皮が食べられて幹が裸状態になっているので、幹ガードで守っていきます。桜の木は美味しいのか、ほかの木よりも被害が多くなっています。
 こちらも鉄筋を2本打ち込み、幹ガードを針金で止めて出来上がりです。
こちらも鉄筋を2本打ち込み、幹ガードを針金で止めて出来上がりです。
56本の木に幹ガードを取り付けました。終了後、来年度(4月)からの「エコ散歩IN足尾」を中心とした森びとプロジェクトの取り組みの大まかな内容が大野運営委員から提案され、意見交換をした後に解散となりました。
本日の作業者は、大野さん、松村宗さん、本間さん、山本さん、橋倉さん、田村さん、柳澤さん、坂口さん、林子さん、田城さん、筆者加賀でした。(報告:加賀春吾)











 伊豆の鎮守の森にあるイチイガシ
伊豆の鎮守の森にあるイチイガシ




















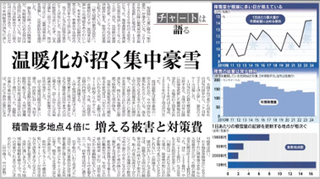




最近のコメント