森に寄り添う暮らしを持続させる人間の責務を果たしたい
明けましておめでとうございます。地球温暖化にブレーキをかけ、未来の子や孫のために「温暖化防止運動」を世界に広める一歩を踏み出すことができましたでしょうか。
昨年暮れの「森びと設立15年感謝の集い」では、15年間支えてくれた皆さんに森づくりの苦労を共にし、新たな希望を感じていただくことができたのではないかと思っています。足尾スタッフは、ふるさとを追い出された松木村村民の想いを心に描き、草木も生えなかった地に木を植え、最低3年間の草刈りを行い、わが子のように木々たちを15年間育ててきました。その木々たちはそれに応え、四季折々に彩り、今を生きるすべての生物たちに“勇気と希望”を与えていることでしょう。
 新年を迎え、AIが人間の知性を超えるといわれる時代に、生物社会の中の小さな人間社会である人間を知り、最大公約数のAIのデータを考え判断することができる五感と知恵を磨き、自然界の想定外の警告と向き合っていくことが求められているのではないでしょうか。
新年を迎え、AIが人間の知性を超えるといわれる時代に、生物社会の中の小さな人間社会である人間を知り、最大公約数のAIのデータを考え判断することができる五感と知恵を磨き、自然界の想定外の警告と向き合っていくことが求められているのではないでしょうか。
 2020年は「パリ協定」開始の年です。締約国の目標を達成しても、世紀末には人類の危機を迎えると言われています。地球に生きる人間として、これからもこの地球上で生きていくための人間としての責務を果たしていきたいと願っています。
2020年は「パリ協定」開始の年です。締約国の目標を達成しても、世紀末には人類の危機を迎えると言われています。地球に生きる人間として、これからもこの地球上で生きていくための人間としての責務を果たしていきたいと願っています。
 私たちの足元をしっかり固めて、東京事務所一同は今年も森づくり現場からその運動をサポートしたいと思います。“森とも”のご多幸をお祈りします。(東京事務所一同)
私たちの足元をしっかり固めて、東京事務所一同は今年も森づくり現場からその運動をサポートしたいと思います。“森とも”のご多幸をお祈りします。(東京事務所一同)



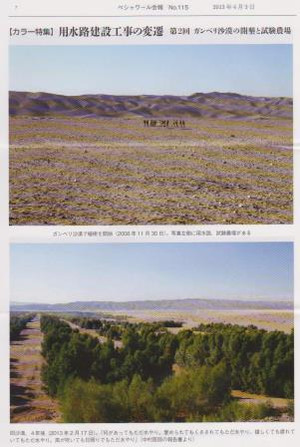
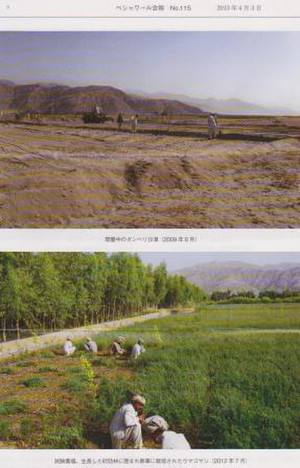





最近のコメント