自然界と人との出会いは森と生きる常識を養う
 2013年調査登山
2013年調査登山
今日も足尾ダム駐車場は満車で、路上駐車があるかもしれない。その多くが中倉山登山者の車かもしれない。登山者は、山頂からの稜線上に生きる「孤高のブナ」(私たちは「無言の語り木」と呼んでいる)に宿る木魂に耳を傾けているのかもしれない。皆さんには人と自然界の“つながり”をつかんでもらいたい。
 2013年夏と秋の調査
2013年夏と秋の調査
先月29日、森びとプロジェクトは「中倉山のブナを元気にする恩送り」を実施した。その報告をホームページで読むと、大雨や雪解けで流される土砂を防ぐブナの根の手入れでは、樹と人との“つながり”を知った方々の常識が活動に現れている気がする。 2013年のブナの実
2013年のブナの実
昨年11月の「ブナを元気にする恩送り」に参加した父親が今年1月に急死、その息子さんが「父の背中を追いかけたい」と思い、4月下旬の恩送りに参加してくれた。また、渡良瀬川下流に住む方は、安心・安全な生活が営めるには上流の足尾の森が元気でないといけないと、足尾での森づくりを手伝いたいと言ってくれた。銅精錬の煙害に耐え抜いて生き抜いているブナと人との出会いが、人と人との“つながり”に結びつき、森と生きる私たちの希望になっているようだ。 2013年夏のブナ
2013年夏のブナ
このブナを発見したのが2012年。その年、足尾の山を知り尽くしている男性から、稜線上に「ケヤキ」が生えているという話を聞いた。標高1500㍍以上にケヤキは生きられるのかと思い、森びとスタッフ松村宗雄さんと私は中倉山に登った。結果、それはケヤキではなくブナであることを確認。翌年の夏と秋にブナの観察を行い、現在に至っている。足尾の山を知り尽くす川口市の男性に出会うことがなければ、年間何百人もの登山者が中倉山の「孤高のブナ」に会いに行くことはなかったと振り返る。
 「みちくさ」での出会いは自然界と人の心を結び付け、人は樹々に恩返しをしながら安全・安心な生活を担保できるという常識が心に育まれていく。自然界と人との大切なつながり”を極端な気象の中でみつけていきたい。(森びとアドバイザー・高橋佳夫)
「みちくさ」での出会いは自然界と人の心を結び付け、人は樹々に恩返しをしながら安全・安心な生活を担保できるという常識が心に育まれていく。自然界と人との大切なつながり”を極端な気象の中でみつけていきたい。(森びとアドバイザー・高橋佳夫)

















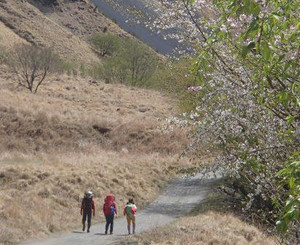


























最近のコメント