アジサイの嫁ぎ先が見えたネット修復
本日、足尾の朝9時の気温6度、少し肌寒い曇り空でした。松木郷も気温の寒暖差が激しい日が続きますが、樹々たちの梢の膨らみは日に日に「もうすぐだね」と、春の囁きが聞こえるるようになりました。
足尾・ダムゲートで森作業の参加者を待っていると3匹の猿に迎えられました。それから程なくして参加者が揃い作業小屋に向かいました。 作業小屋では、ストーブに火を入れてくれていました。そして4人で暖かいコーヒーを飲みながら打ち合わせを行い、今日の森作業は、アジサイを覆っていたネットの修復と剪定を行うことにしました。
みちくさ庭に4人で行って見ると2月、3月に降った雪に重みで、アジサイを食害から守るために覆っていたネットがすべて落ちてアジサイの芽の生長を邪魔していました。
先ずどこから始めるか話し合いました。
庭の西側から始めることにしました。ネットを支えていた竹が使えるか点検し、支柱に横の竹を紐で縛り付け骨組みをつくりました。それでも少しグラついているので、何か所かの支柱に紐をつけて獣害柵のパイプに縛り動かないようにしっかりさせました。
12時を回ったので昼食にしました。
午後は、柳澤さんが真竹4mもの約60本をトラックに積んで持ってきてくれましたので、トラックから降ろしてうんしゅう亭に保管しました。
午前中の続きで庭のアジサイ畑のネット修復を行いました。作業中に庭の獣害柵が何物かに破られていたのを見つけたので、新しい柵を持ってきて修繕しました。その後、アジサイがあまりに密集していて大変でしたが、枯れた枝など剪定しました。3人の恐るべきパワーに感動しました。
森作業終了後ミーティングではアジサイの本数があまりに多すぎるので移植してはどうか、100本位か、多すぎるので栄養不足か、などの話がありました。矢口さんからは移植するなら秋が良いのではと提案がされました。検討することにして終了しました。お疲れ様でした。
本日の森作業は、清水、柳澤、矢口、そして大野でした。
<報告は大野昭彦>























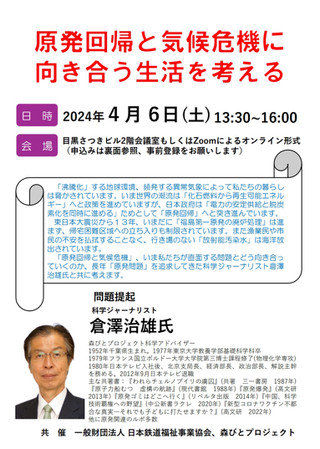
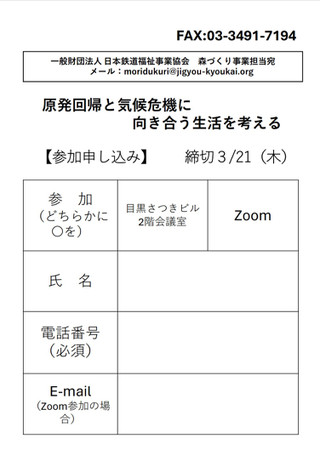
































最近のコメント