新緑の中、森の散策で将来の森づくりを考える
本日の8時40分の足尾・松木沢は、気温3℃。快晴で風が少しあり肌寒く感じましたので、作業小屋の薪ストーブに火を入れました。
 9時からの打ち合わせで責任者の大野さんから「本日は、森作業を行なわないで自分たちが作ってきた森の中に入り、今年から始まるりんねの森づくりを考えましょう」との説明があり、ホットコーヒーを飲みながらこれまでの森づくりの感想を出し合いました。
9時からの打ち合わせで責任者の大野さんから「本日は、森作業を行なわないで自分たちが作ってきた森の中に入り、今年から始まるりんねの森づくりを考えましょう」との説明があり、ホットコーヒーを飲みながらこれまでの森づくりの感想を出し合いました。
 柳澤さんから「2004年秋の時はススキだらけだった。当時を思うと、ずいぶん変わった」と森づくりの最初のころの苦労話が出されました。
柳澤さんから「2004年秋の時はススキだらけだった。当時を思うと、ずいぶん変わった」と森づくりの最初のころの苦労話が出されました。
(写真)2004年9月の足尾
早速、木々の生長を確認するために、17年経った臼沢の森に入りました。そして、M&mのベンチに座り、森を見ながらこれからの森づくりを考えました。
次に臼沢西の森に入り、昨年から始まった里親植樹地を見ました。ウサギの仕業と思われますが、苗木が一定の高さで切られていました。動物たちとの知恵比べとはいえ、私たちの苗木に向かう姿勢が問われ、人間の都合で森づくりは出来ない、と改めて感じました。
 昼食後の話し合いでは、「今後の森づくりについて森としてうっそうとしているが、木々がひょろっとしており細い」、「平和でないと森づくりはできない」等の意見が出されました。
昼食後の話し合いでは、「今後の森づくりについて森としてうっそうとしているが、木々がひょろっとしており細い」、「平和でないと森づくりはできない」等の意見が出されました。
 最後に大野さんから「自分の森として活動していきましょう」との言葉を参加者で確認して、本日の新緑の森の散策会を終了しました。
最後に大野さんから「自分の森として活動していきましょう」との言葉を参加者で確認して、本日の新緑の森の散策会を終了しました。


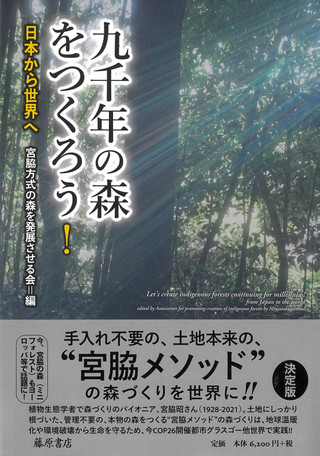

最近のコメント