本日11月3日(水)、足尾『中倉山のブナを元気にする恩送り』を開催し、森びとスタッフと森ともの皆さん28名で「無言の語り木」“孤高のブナ”に元気を届ける活動を行いました。新型コロナウイルス感染者数が減少傾向にありますが、感染予防に努め取り組みました。

足尾ダムゲートに7時に集合。久蔵川にかかる橋を渡り、「足尾に緑を育てる会」にお借りした広場に参加者の車を駐車させていただきました。
そこから、登山口を目指し、仁田元川沿いの道路を1時間ほど歩くと登山口に到着。森びとスタッフが出迎えてくれました。天候は秋晴れとなり、絶好の登山日和となりました。

登山口でブナの根を保護するための黒土10ℓ1袋と植生袋2枚を参加者に持っていただき、コロナ感染予防のため、少人数のグループに分けて距離を保ちながら中倉山山頂を目指しました。地上スタッフを除く24名でブナを目指しました。

つづら折りの登山道を登ると木々の葉も色づき、足もとには落ち葉が積もり始めています。枯葉で足を滑らせないように注意しながら登りました。こまめに休憩を取り、水分補給をしながら登りました。


登りはじめて1時間、最初の尾根に到着し小休憩をとりました。南の山々の斜面は紅葉のピークは過ぎたようですが、黄や赤が点在し、遠くには頂が雪で真っ白な富士山を眺めることができました。木々の彩を楽しみながら登り続けて2時間。10時に中倉山の尾根に到着しました。煙害に耐え、現在は気候変動に耐え生きる「無言の語り木」“孤高のブナ“が私たちを待っていました。





24名の参加者が全員到着し、リュックから黒土の袋を取り出してもらい、済賀スタッフ、鎌田サポーター、矢野さんが植生袋づくりのデモンストレーションを行った後、2人一組となり植生袋に黒土を詰めました。30枚の植生袋をブナの北斜面の土壌がむき出しとなっている場所に張り付けました。







2018年から張り付けた植生袋は周りの笹や草と一体化しており、根で土壌を押さえています。
ブナの根を守るため登山ルートに張っている麻ロープが劣化し、所々切れており、大塚さんと小川さんが張り替えてくれました。

ブナを見ると葉を落とし始め、冬に備えているようです。枯れた枝も見受けられ、厳しい環境下で耐えるブナの「叫び」が聞こえてくるようです。

遠目にブナを眺めると、ブナの生える北側に草のエリアが広がっていますが、東西の北斜面は崩壊が止まらないようです。日光森林管理署の徳川署長、伊藤森林官に斜面の状況を見ていただきましたが、まだまだ崩壊地は広く、市民やボランティアの努力には限界があり、国有林を管理する林野庁や自治体など行政が「本気」になり、崩壊地の土砂の流失を止め、緑化していかなければならないと感じました。


作業終了後、全員で集合写真を撮影しました。その後、徳川署長からご挨拶、参加者から感想をいただき、森びとを代表して副代表の清水からお礼を述べました。






早めの昼食をとり、11時に下山を開始しました。尾根伝いを戻り、ツツジのトンネルをくぐり抜けていきます。



北側の松木川沿いに目を向けると、森びとプロジェクトの植栽地、臼沢の森や松木の杜、民集の杜の木々が色づき、一幅の絵画を見るようです。森の中では落ち葉を食べ分解する土壌動物が忙しく働き始め、冬に備え木の実を食べ、命をつなぐ動物たちの営みもおこなわれていることでしょう。
まだまだ荒廃地は広く、温室効果ガスの吸収源であり、いのちの源でもある森づくりは世界的な取り組み課題です。英国グラスゴーに各国の首脳が集まり「国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)」が開催されました。(10月31日~11月2日)温室効果ガス排出削減と同時に、吸収源である森と海を元気にする政策目標も一致させて欲しいと願います。

12時30分に登山口に到着。登山口に待機している加賀さんから参加者の皆さんに冷やした紙パックのジュースが配られ、乾いた喉を潤しました。


本日の「中倉山のブナを元気にする恩送り」参加者の車を止める駐車スペースを提供していただきました「足尾に緑を育てる会」の皆さま、横断幕作成に協力をいただきましたJREU大宮の皆さま、同行していただきました日光森林管理署・徳川署長様、伊藤様、共同通信社・鰍澤様、大変ありがとうございました。本日参加していただいた皆さま大変お疲れ様でした。

本日の参加者は、徳川さん、伊藤伸さん、鰍澤さん、野澤さん、福田さん、伊藤典さん、木村邦さん、目黒さん、鎌田順さん、荒川さん、ザイさん、カエルさん、矢野さん、木村有さん、鈴木さん、山田さん、山内さん、大川さん、鎌田さん、大塚さん、橋倉さん、加賀さん、小川さん、弘永さん、坂口さん、済賀さん、そして筆者でした。(報告・清水)
 さらに、足を延ばして春に訪れた「泉中央自然公園」に行き、植樹した木々たちを見てきました。植えた木々は樹高3㍍位に伸び、周りの森に溶け込んでいました。カエデ類の葉が赤色や黄色に染まり、池の水面にはその輝きを映し出していました。池にはカモが泳ぎ、紅葉を楽しんでいるようでした。まるで絵画を見ている気持ちになりました。
さらに、足を延ばして春に訪れた「泉中央自然公園」に行き、植樹した木々たちを見てきました。植えた木々は樹高3㍍位に伸び、周りの森に溶け込んでいました。カエデ類の葉が赤色や黄色に染まり、池の水面にはその輝きを映し出していました。池にはカモが泳ぎ、紅葉を楽しんでいるようでした。まるで絵画を見ている気持ちになりました。
 コロナ感染拡大が落ち着いていますので、自粛生活での閉塞感を和らげてくれたのが木々でした。生きていく過程で木々の働きを、改めて有難く思っています。
コロナ感染拡大が落ち着いていますので、自粛生活での閉塞感を和らげてくれたのが木々でした。生きていく過程で木々の働きを、改めて有難く思っています。
 また、その恩返しのようになりましたが、先月行った南房総の「花嫁街道」の修繕と、台風で倒れた材でベンチを設置したボランティアが夫婦の気持ちを豊かにしてくれています。そのようなことを語り合える散歩ができることに感謝です。
また、その恩返しのようになりましたが、先月行った南房総の「花嫁街道」の修繕と、台風で倒れた材でベンチを設置したボランティアが夫婦の気持ちを豊かにしてくれています。そのようなことを語り合える散歩ができることに感謝です。
































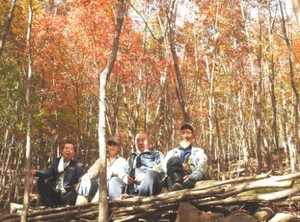

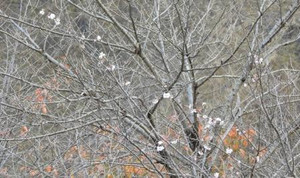












































































最近のコメント